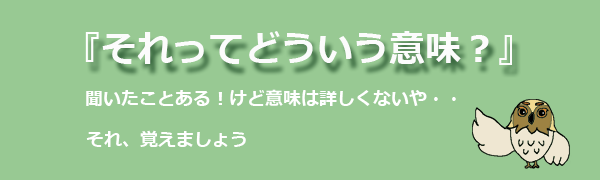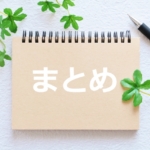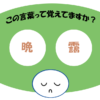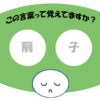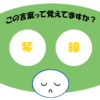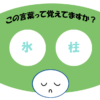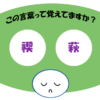「巻繊」の意味と読み方とは?ヒントは「料理」
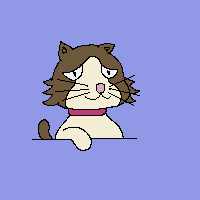
巻繊って、なんと読むのかな??
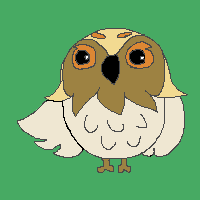
「巻繊」はね、「けんちん」と読むんだよ。
巻繊の意味
《「ちん(繊)」は唐音》椎茸 (しいたけ) ・ごぼう・にんじんなどをせん切りにして味付けをし、湯葉で巻いて油で揚げたもの。現在は、つぶした豆腐を野菜とともに油で炒め、醤油・酒などで調味したものをいう。元来は禅僧が中国から伝えた普茶 (ふちゃ) 料理。
出典 デジタル大辞泉(小学館)
巻繊はここに注意
「繊」の読み方に注意しましょう!
言葉の難しさ・・・★★★☆☆
読み書きが少し難しいため。
すぐ忘れてしまいそう?それなら・・・
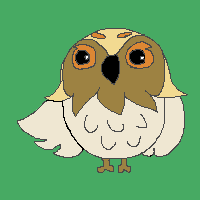
つまり「巻繊」の意味は、ごぼうやにんじんなどをせん切りにして味付けし、湯葉で巻いて油で揚げたものなんだね。
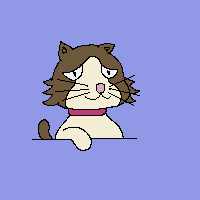
「繊」って、「ちん」とも読むんだなぁ・・・。
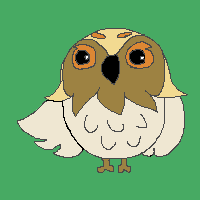
そうなんだ、だから読み方を間違えないようにしたいね。
「巻繊」の「巻」は他に「かん・巻く・まき」とも読みますよね。意味は、
- まきもの。「巻軸」など
- 書物。「圧巻」など
- まいた物や書物を数える語。「万巻」など
- まく。
- 曲がる。
- にぎりこぶし。
となっています。書物の意味もありますよね。
「繊」は他に「せん・繊い・繊さい・繊やか」とも読みます。意味は、
- ほそい糸。「繊維」など
- ほそい。ちいさい。「繊細」など
- こまかい。しなやか。「繊手」など
となっています。細く小さいようですね。
細く切ったニンジンなどを湯葉で巻いて、油で揚げたものをイメージして「巻繊」と覚えておきましょう!
巻繊汁という料理もありますよね!😁
「巻」の部首である「己」は、字形から文字を整理するために設けられた部首とのこと。
上部は分散しかけたものの象形、その下は両手の象形。さらに、下部は膝を曲げている人の象形となっているそう。
このことから、丸く巻いたり束ねる意味で「巻」が成り立ったと言われています。
「繊」の部首は「糸」で、糸の形状や種類などに関する字に主に使われますね。
糸を細かく分けた様子をあらわして「繊」が成り立った、という話がありますよ。🧵
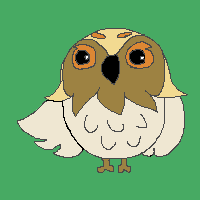
今は、料理の形が変化しているみたいだね。
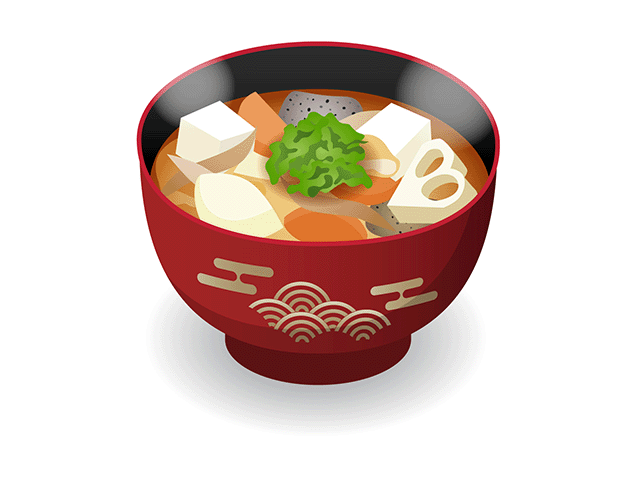
この言葉、どう使う?
- 初めて、巻繊という料理を食べた。
「巻繊」の熟語・ことわざ・慣用句
- 巻繊汁・・・つぶした豆腐とせん切りにした野菜を油で炒め、澄まし汁仕立てにしたもの。
- 巻繊蒸し・・・つぶした豆腐とせん切りにした野菜を油で炒め、背開きにした小鯛 の腹に詰めて、せいろで蒸した料理。
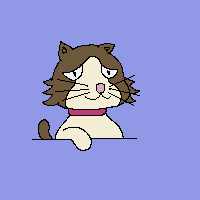
確かに、細くして巻いたものだからこの漢字で良いのか・・・。
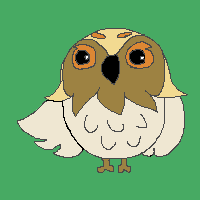
あまり漢字で見ることは無いから、少し難しいだろうね。
まとめ
「巻繊」は、ごぼうやにんじんなどをせん切りにして味付けし、湯葉で巻いて油で揚げたものなんですね。
細く切ったニンジンなどを湯葉で巻いて、油で揚げたものをイメージして覚えておきましょう!
巻繊汁という料理もあるので、まずはどういった料理かを覚えることから始めても良さそうです!😁
「巻」の部首の「己」は、字形から文字を整理するために設けられた部首だそうですね。
上は分散しかけたもの、その下は両手、さらに下は膝を曲げている人の象形とのこと。
このことから、丸く巻いたり束ねる意味で成り立ったと言われていますよ。
「繊」の部首は「糸」で、糸の形状などに関する字に主に使われますね。
糸を細かく分けた様子をあらわして成り立った、という話があります。🧵
こちらはいかがでしょうか?
色んな野菜を調理するのが面倒・・・。
こちらは香り豊かな山菜<わらび・しいたけ>、鶏肉、油揚、こんにゃく、車麩、それに数々の新鮮な野菜を美味しく煮込んであります。
缶詰なので、保存もできますね!
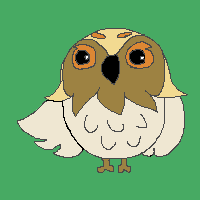
これも、ひらがなで書かれているね。